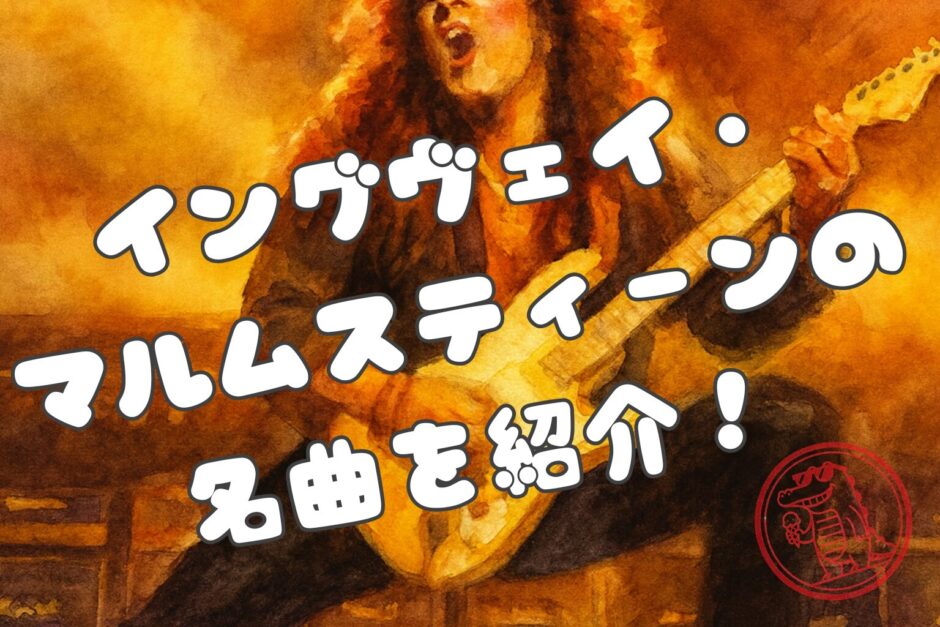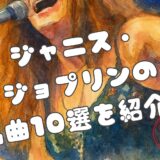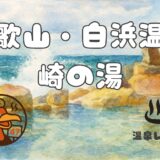クラシックの様式美とヘヴィメタルの激情を融合させ、ギターの表現を一段階上の次元へと引き上げたギタリスト。それがイングヴェイ・マルムスティーンです。速弾きの王者と称され、その独自の美学と圧倒的な技巧で、世界中のギタリストたちに衝撃を与えてきました。
本記事では、そんなイングヴェイによる名曲10曲を厳選しました。アルバム紹介は以下の記事で行っていますので、ご興味のある方はあわせてご覧ください。
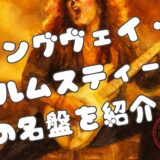 【まずはこれ】イングヴェイ・マルムスティーンの名盤7選|ネオクラシカルの歴史を辿る傑作たち
【まずはこれ】イングヴェイ・マルムスティーンの名盤7選|ネオクラシカルの歴史を辿る傑作たち目次
- 1.イングヴェイ・マルムスティーンの名曲10選
- (1)「Far Beyond The Sun」:インストの金字塔
- (2)「Trilogy Suite Op:5」:暴君に宿る叙情性
- (3)「Black Star」:初期の衝撃
- (4)「You Don’t Remember, I’ll Never Forget」:ボーカル曲の代表格
- (5)「Heaven Tonight」:キャッチーさとテクニックの融合
- (6)「I’ll See The Light Tonight」:疾走感あふれる名曲
- (7)「Vengeance」:攻撃的なサウンド
- (8)「Dreaming (Tell Me)」:叙情的なバラード
- (9)「Never Die」:力強いアンセム
- (10)「Caprici Di Diablo」:後期の名演
- 2.イングヴェイ・マルムスティーンの名盤
- 3.まとめ:初心者も、かつてのギター少年も、もう一度イングヴェイを聴いてみよう
1.イングヴェイ・マルムスティーンの名曲10選
(1)「Far Beyond The Sun」:インストの金字塔
「Far Beyond The Sun」は、クラシックとメタルを激しく交錯させた様式美のなかに、感情の起伏を刻むようなチョーキングや緩急あるソロが詰め込まれています。速さだけじゃない究極の芸術性が魅力。
鍵盤とのスリリングな応酬、そして小節の概念すら振り切る終盤のブレイクでは、理性と狂気がせめぎ合うような凄まじさを堪能できます。
ちなみに、この曲が発表された当時のイングヴェイは、北欧の美しい王子様そのもの。その外見と超絶技巧のギャップも、多くのファンを虜にしたことでしょう。
| リリース | 1984年 |
| 収録アルバム | 『Rising Force』 |
(2)「Trilogy Suite Op:5」:暴君に宿る叙情性
「Trilogy Suite Op:5」は、アルバム『トリロジー』のラストを飾る激しくも美しい曲です。
切れ目なく流れるユニゾンフレーズから、まるで花が開くように様式美が展開していく構成は圧巻です。
途中に挿入されるガットギターのパートでは、エレキとは異なる繊細な叙情がにじみ出ており、イングヴェイの表現力の奥行きを感じさせます。
| リリース | 1986年 |
| 収録アルバム | 『トリロジー』 |
(3)「Black Star」:初期の衝撃
ソロデビュー作『Rising Force』の幕開けを飾る「Black Star」は、イングヴェイという革新的なギタリストの存在を世に知らしめた名インストです。
抒情性を湛えたスローな導入から、音の厚みを増しつつ炸裂するスウィープ、そして12〜14連符の超絶速弾きへと展開する構成は、まさにギター界に黒い彗星が舞い降りてきたかのよう。
ゆったりしたテンポでも一瞬たりとも間延びしないその説得力に、繊細な表現力がはっきりと刻まれています。
| リリース | 1984年 |
| 収録アルバム | 『Rising Force』 |
(4)「You Don’t Remember, I’ll Never Forget」:ボーカル曲の代表格
「You Don’t Remember, I’ll Never Forget」はシンセサイザーと絡み合う鋭くクラシカルなリフが印象的な、イングヴェイの代表的ボーカル曲(※イングヴェイが歌ってるわけではありません)。
ギターソロでは、アームを効かせたエモーショナルなヴィブラートと、流れるようなクラシカル・フレーズが炸裂します。高速でも旋律の美しさを失わないその圧倒的な完成度は、技巧を超えた“音楽的説得力”そのもの。
| リリース | 1985年 |
| 収録アルバム | 『トリロジー』 |
(5)「Heaven Tonight」:キャッチーさとテクニックの融合
疾走するインストの印象が強いイングヴェイですが、実はハードロック路線でも一級品です。
『Odyssey』収録の「Heaven Tonight」は、ジョー・リン・ターナーのソウルフルな歌声と絶妙に噛み合い、キャッチーかつメロディアスな仕上がりに。
ギタリストとしてだけでなく、ソングライターとしての表現力が花開いた一曲です。なお作詞はジョー・リン・ターナー担当のようです。
| リリース | 1988年 |
| 収録アルバム | 『オデッセイ』 |
(6)「I’ll See The Light Tonight」:疾走感あふれる名曲
「I’ll See The Light Tonight」は、荒々しくも力強いイングヴェイ初期の魅力が詰まった代表曲のひとつ。
イントロのリフは、一度聴けば忘れられないキャッチーさで、ジェフ・スコット・ソートのシャウトとも抜群の相性を見せています。リフメイカーとしての才覚と、楽曲全体に漲るエネルギーが心を揺さぶります。
| リリース | 1991年 |
| 収録アルバム | 『マーチングアウト』 |
(7)「Vengeance」:攻撃的なサウンド
「Vengeance」はクラシカルな気品を帯びたイントロのガットギターから一転、怒涛のリフと怒りのようなソロが炸裂する、ネオクラシカル疾走チューンの代表格。
ハーモニックマイナーとペダルフレーズが火を噴くように駆け抜け、ギターソロの入りはドラマティックの極み。
マイク・ヴェセーラのストレートな歌唱も相まって、イングヴェイの暴君ぶりが全開となった劇的な一曲です。
| リリース | 1995年 |
| 収録アルバム | 『マグナム・オーパス』 |
(8)「Dreaming (Tell Me)」:叙情的なバラード
「Dreaming (Tell Me)」は哀しみを湛えたバラードで、ジョー・リン・ターナーの声とイングヴェイの旋律美が深く響き合う一曲。
ギターソロの入り口では、語りが始まりそうな演歌調のアコースティックが情感を誘い、そこから一気に“激泣き”フレーズが畳みかけてきます。
クラシカルかつトレブリーなギタートーンがメロディを際立たせ、短いながらも胸を打つ名演に仕上がっています。
| リリース | 1988年 |
| 収録アルバム | 『オデッセイ』 |
(9)「Never Die」:力強いアンセム
「Never Die」は、クラシカルなハーモニック・マイナーを軸にした激しいイントロから、マイク・ヴェセーラの力強い歌声で一気に展開します。流れるようなフレーズ運びとアグレッシブなヴィブラートが融合したギターソロは、まさに暴走するクラシックにふさわしい名演です。
ピッキングのニュアンスまで繊細に計算された音作りが、ただ速いだけではない音楽としての速弾きを体現しています。
| リリース | 1994年 |
| 収録アルバム | 『Seventh Sign』 |
(10)「Caprici Di Diablo」:後期の名演
後期イングヴェイの代表的インストゥルメンタルで、冒頭から超絶技巧が炸裂。
6弦スウィープやスリリングな速弾きを前面に出しつつ、メロディやコード進行にも工夫が見られ、弾きまくりに終わらない構成美が光ります。勢いだけでなく、表現としての緻密さを備えた、まさに円熟の名演です。
なおタイトルの「Caprici Di Diablo」はイタリア語とスペイン語を混ぜたような造語で、悪魔の奇想曲といった意味合いです。クラシック由来の技巧とメタルの破壊力を象徴するようなネーミングセンスが光ります。
| リリース | 2008年 |
| 収録アルバム | 『パーペチュアル・フレイム』 |
2.イングヴェイ・マルムスティーンの名盤
名曲を深く味わいたいなら、アルバム単位で聴くのもおすすめです。
ここでは名曲が多数収録された代表的な名盤を一覧で紹介します。
| アルバム | 発売年 | 特徴 |
|---|---|---|
| Rising Force | 1984年 | 衝撃のソロデビュー作。 ネオクラシカルの原点 |
| Trilogy | 1986年 | 哀愁と技巧が融合。 初期の集大成 |
| Odyssey | 1988年 | ジョー・リン・ターナーとの 名コンビ |
| The Seventh Sign | 1994年 | ドラマ性のある中期の傑作 |
| Magnum Opus | 1995年 | 重厚な王道メタルと叙情性の融合 |
| Perpetual Flame | 2008年 | 復活の後期傑作。攻撃性が再燃 |
3.まとめ:初心者も、かつてのギター少年も、もう一度イングヴェイを聴いてみよう
イングヴェイ・マルムスティーンは、クラシック音楽とヘヴィメタルを融合させた“ネオクラシカル・スタイル”の確立者として、音楽史に確かな足跡を残しました。
誇り高く、妥協を許さず、徹底して自らの美学を貫く。それがイングヴェイ・マルムスティーンという存在です。
もう一度あの圧倒的なサウンドに触れると、唯一無二のギターサウンドが心に火を灯してくれるでしょう。